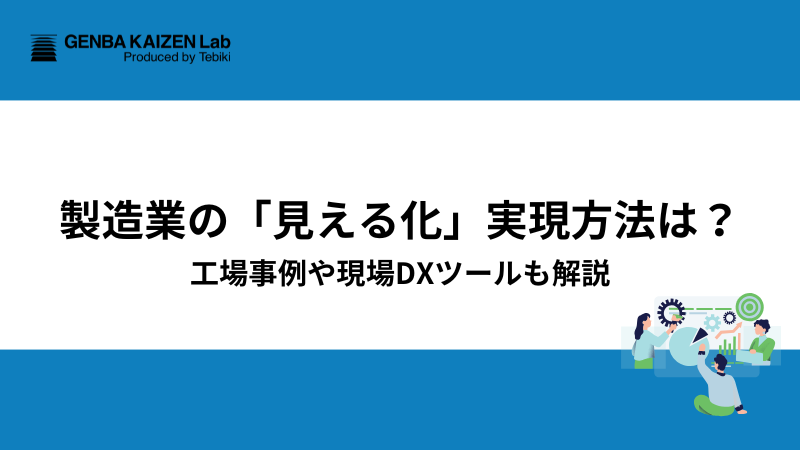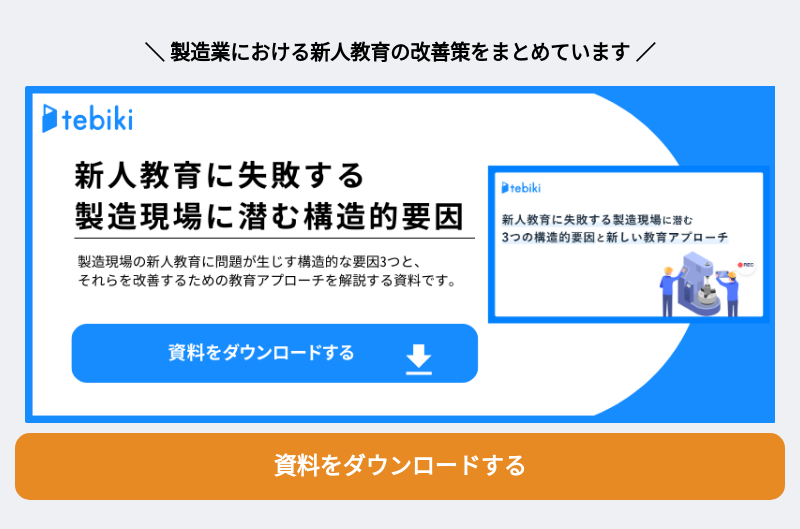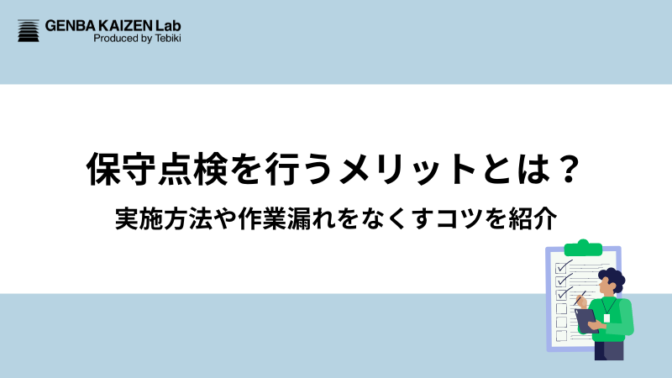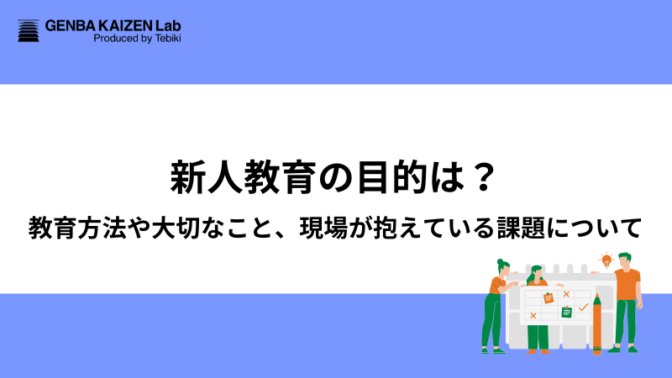かんたん動画マニュアル作成「tebiki現場教育」や、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。
製造業における「見える化」とは、「工程・進捗」の可視化と、「技術・業務(ノウハウ)」の可視化を指します。これら2つを見える化する手段が「データ」です。
本記事では、データを通じた工場の見える化がもたらすメリットと見える化の実践方法、見える化に必要な2つのツールについて解説します。
※工場の状態を見える化する手段の1つに「ディスプレイの設置」がありますが、ディスプレイ設置による見える化の改善効果や実例を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:工場を「見える化」するディスプレイ活用事例4選と必須システム
目次
製造業や工場現場における「見える化」とは?
製造現場における「見える化」とは、以下の2つを指します。
- 「工程・進捗」の見える化
- 「技術・業務(ノウハウ)」の見える化
これら2つをデータやツールを用いて可視化することが、製造現場における見える化です。単に工場内の数値をグラフなどで表示するようなことではありません。
製造現場の課題を解決し、生産性向上、品質向上、コスト削減、そして技術伝承を促進する目的を果たすための戦略的な取り組みが見える化であり、工場の発展に不可欠です。それぞれの見える化について詳しく解説します。
「工程・進捗」の見える化
「工程・進捗」の例として、以下のような項目が挙げられます。
- 生産数
- 進捗状況
- 不良率
- 設備の稼働率
- 在庫状況
これらのデータを、リアルタイム、またはそれに近い形で把握できるようにすることが見える化につながります。
「工程・進捗」が可視化されれば、生産現場の「今」が詳細に分かり、問題発生の予兆を捉えたり、ボトルネックとなっている箇所を特定したりすることが可能になります。つまり、工場全体の生産性向上に重要である「現状の把握と対策の実行」が迅速に実行できるようになるのです。
「技術・業務(人)」の見える化
技術・業務(人)とは、以下のような項目を指します。
- 従業員個々の技術やスキル
- 複雑な作業手順や暗黙知
- 安全作業
- 作業時間(タクトタイム)、作業負荷
これらを目に見える形にすることが見える化につながります。
技術や業務の見える化ができると、暗黙知を形式知化できたり、技術伝承や多能工化が促進されます。これらが実現されると作業標準化が図られ、属人化の解消や工場全体の生産性向上を生み出すのです。
「見える化」によって製造業の何が変わる?具体的なメリット
工場における工程や人を「見える化」することで、現場の課題解決はもちろん、経営全体の改善にも繋がる、以下のようなさまざまなメリットが得られます。
- データに基づいた意思決定
- 技術継承による属人化解消
- 生産性と品質の向上
データに基づいた意思決定
「見える化」によって、これまで頼りがちだった勘や経験ではなく、客観的なデータに基づいた意思決定が可能になります。
例えば、生産実績、不良率、設備の稼働率といったデータをリアルタイムで把握することで、問題の原因を迅速に特定できます。さらに、過去のデータとの比較分析を通じて、実施した改善策の効果を定量的に評価することも可能です。これにより、需要予測の精度が向上し、より現実的かつ効率的な生産計画の立案に繋がります。
関連記事:【DX促進】製造業におけるデータ活用の進め方とは?メリットや成功事例について解説!
技術継承による属人化解消
ベテラン社員が持つ技術やノウハウを「見える化」することは、製造業における経営課題でもある「属人化」の解消に大きく貢献します。
ノウハウの見える化の例として、ベテラン社員のカンコツ作業を視覚的に伝えられる「動画マニュアル」が挙げられます。これにより、紙マニュアルや文字ではなかなか教えられなかった「複雑な技術」「カンコツ」の教育が可能になり、技術伝承がスムーズに進みます。
例えば、紡績から縫製、販売までを行う「御幸毛織株式会社」では、熟練者による機械操作と技の連携に品質が支えられている一方で、熟練者の高齢化による技術伝承に課題を抱えていました。具体的には以下のような課題です。
- 新卒採用をストップしていた時期があり、社員の年齢分布に偏りがある
- 製品は職人の微妙なコントロールによって成せる品質に支えられていた
- 特定の工程で低品質な作業が行われると、全工程に影響が及ぶため全体で高品質が必要
こうした課題を解消すべく、同社は「熟練者が持つ技術の見える化」を実施し、現在は技術継承を促進しています。詳しい事例や見える化の推進方法は、以下の事例インタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:明治時代創業の繊維会社が挑む技術伝承!ITテクノロジーを駆使して伝統芸を若手へ伝達
技術継承の体制整備は、製造業の経営課題に直結します。もし技術継承に課題感がある場合は、以下のPDF資料や無料セミナー動画を参考にすると、技術継承の推進ヒントが得られるはずです。ご覧いただきやすい方をダウンロードしてみてください。
>>>「熟練者の技術伝承を成功させるポイント」がまとめられた資料を読んでみる
>>>「トヨタ式技能伝承の推進方法」が分かる無料セミナー動画を視聴する(元トヨタ技能者による解説)
生産性と品質の向上
「見える化」は、生産プロセス全体に潜むムリムダムラを明らかにし、生産性と品質の向上に貢献します。
例えば、設備の稼働状況を常に監視することで、チョコ停(短時間の停止)の原因を特定し、対策を講じることが可能です。また、不良品の発生状況を工程ごとに可視化することで、原因を特定し、再発防止策を徹底できます。さらに、各工程の作業時間を計測することで、ボトルネックとなっている工程を特定し、改善を図ることも可能です。
生産性や品質の改善方法は多種多様に存在するので、まずは現場に合った改善を実施しましょう。何から手を付けていいか分からない場合は、専門家や元現場責任者による品質改善の無料セミナーを参考にしてみるのも1つの手です。以下のリンクでは製造業の現場改善に向けた品質改善セミナーの一覧がまとめられているので、参考にしてみてください。
>>>「生産性や品質改善に関する無料オンラインセミナー」の一覧を見てみる
製造業の「見える化」の導入・運用における課題や注意点
「見える化」は、製造業に多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用には5つの課題や注意点が存在します。
- データ収集・分析の基盤が構築されていない
- 属人化している業務のノウハウやカンコツを可視化できない
- 見える化の目的が漠然としている
- データに紐づいた継続的な改善活動(PDCAサイクル)が回らない
- 最初から組織全体を改革しようとする
これらを事前に理解しておくことで、「見える化」の取り組みをよりスムーズに進め、効果を最大化することができます。それぞれ詳しく解説します。
データ収集・分析の基盤が構築されていない
「見える化」の第一歩は、現場のデータを収集・分析することですが、多くの製造現場では、データを集計するための基盤がそもそも整っていないという課題があります。見える化がなかなか実現できない現場には、例えば以下のような共通点が存在します。
- データが紙の帳票やExcelで管理されており、収集・集計に手間がかかる
- データが様々なシステムに分散しており、一元管理されていない
- データの精度が低い、または信頼性に欠ける
このような状況では、「見える化」を始めても、効果的な分析や改善に繋がらず、時間と労力の無駄になってしまう可能性があります。まずはデータ集計基盤の構築からスタートするのが良いでしょう。
属人化している業務のノウハウやカンコツを可視化できない
ベテラン従業員が持つノウハウやカンコツは、製造業にとって貴重な財産ですが、これらは属人化しやすく、「見える化」が難しいという課題があります。というのも、製造現場では高度な専門性やスキルが求められ、複雑な作業手順が多いからです。
しかし、ベテラン社員個々のスキルを可視化できなければ、新入社員や中途社員は即戦力化できず、ベテラン社員がいなければ工場全体が回らないというリスクが徐々に膨らんでいくことになります。
属人化がなかなか解消されないのは「新人教育の体制がうまく整備されていない」ことが主な要因の1つですが、新人教育に失敗する製造現場には3つの構造的要因が潜んでいます。詳細を知りたい場合は、以下の画像をクリックしてPDF資料「新人教育に失敗する製造現場に潜む3つの構造的要因と新しい教育アプローチ」もあわせてご覧ください。
見える化の目的が漠然としている
「見える化」の目的が曖昧なまま、ツール導入やデータ収集を始めてしまうと、効果が得られず、失敗に終わる可能性が高まります。例えば以下のようなケースです。
- 「何となく」見える化を始めてしまい、何を改善したいのかが明確でない
- 経営層と現場で「見える化」の目的が共有されておらず、現場がやらされ感を持ってしまう
- KPI(目標)が設定されておらず、効果測定ができない
目的が不明確なままでは、現場の協力も得られにくく、プロジェクトが頓挫してしまう可能性があります。
データに紐づいた継続的な改善活動(PDCAサイクル)が回らない
「見える化」は、一度導入して終わりではありません。むしろ、収集・分析したデータを基に、継続的に改善活動(PDCAサイクル)を回していくことがより重要です。あらゆる事象を見える化しただけでは、現場の生産性向上にはつながらないからです。
客観的データに基づいた対策を講じて初めて変化が生まれます。そしてその変化を評価し、さらなる打ち手を立案・実施し続けるサイクルが回ることが重要です。
例えば「株式会社日本電気化学工業所」では、データの蓄積と分析が可能な体制を工場内で構築しましたが、構築して終わることなく、データを都度見ながら、生産活動における中長期的な対策の立案・実施サイクルを回せるようになっています。常にデータを蓄積・分析し、迅速な対策に動けるような体制ができているからこそ、PDCAサイクルを通じた改善活動を実現できているのです。同社の詳しい「見える化」事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現。異常値検知を迅速にできた理由。
最初から組織全体を改革しようとする
「見える化」を成功させるためには、段階的な導入が重要です。最初から組織全体を改革しようとすると、現場の混乱を招き、失敗するリスクが高まります。一度に多くのデータを見える化しようとしたものの、収集・分析が追い付かない、というような事態は避けなければなりません。
また、新しい見える化システムを導入したものの、現場が使いこなせないというような失敗例も少なくありません。現場が大きければ大きいほど、段階的な取り組みが重要になります。
製造業や工場を「見える化」する5つの実践ステップ
「見える化」の取り組みは、最初から完璧を目指すのではなく、小さく始め、成功体験を積み重ねながら、徐々に範囲を広げていくことが重要です。ここでは、製造現場の「見える化」を成功に導くための実践的なステップ5つを解説します。
- 課題を洗い出す
- 見える化の適用範囲を決める
- ゴールを設定する
- 手段を検討する
- 運用・振り返りを行う
課題を洗い出す
まずは、自社の製造現場が抱える課題を洗い出すことから始めましょう。課題の発見にはいくつかのやり方がありますが、ここでは4つ紹介します。
- 現場へのヒアリング
- なぜなぜ分析
- 特性要因図(フィッシュボーン)の活用
- 5M分析
現場でのヒアリングは重要なので必須ですが、聞き出した課題を裏付けるための分析も必要です。そこで、なぜなぜ分析や特性要因図(フィッシュボーン)の活用、5M分析を検討してみましょう。詳しいやり方は上記のリンクをクリックしてご覧ください。必要なテンプレート等もダウンロードいただけます。
比較的実施しやすいのは「なぜなぜ分析」なので、ひとまず何らかの行動を起こしたいという場合はなぜなぜ分析の実践をおすすめします。根本的原因を突き止めるためのなぜなぜ分析はコツがいるので、以下の画像をクリックしてPDF資料「【事例で解説】トヨタ流「なぜなぜ分析」の実践方法とポイント(解説動画あり)」を参考にしながら実践してみてください。
見える化の適用範囲を決める
洗い出した課題の中から、最初に取り組むべき課題を選び、「見える化」の適用範囲を決めます。最も効果が出やすいと思われる課題、または最も困っている課題から優先的に取り組みましょう。最初は、特定の工程や特定の設備など、範囲を限定して始めるのがおすすめです。関係者の協力が得られやすい範囲から始めるのも良いでしょう。
例えば以下のように設定します。
- 「A製品の製造ラインにおける不良率が悪化しているので、改善が必要そうだ」
- 「B設備の稼働率が悪化しているので、向上させたい」
- 「Cさんの作業品質にバラつきがあるので、業務標準化したい」
ゴール(目標)を設定する
「見える化」の目的を明確にするために、具体的なゴール(目標)を設定します。ステップ2で決定した「見える化」の対象範囲に基づいたゴールを設定することになりますが、これはできる限り「具体的な目標」にすることがポイントです。数値による目標設定が可能な場合は、数値目標を取り入れることをおすすめします。
ステップ2の課題に対する目標例をまとめると、以下のようになります。
- 「〇ヶ月以内に、A製品の製造ラインにおける不良率を〇%削減する」
- 「〇ヶ月以内に、B設備の稼働率を〇%向上させる」
- 「〇ヶ月以内に、Cさんの作業手順を標準化し、〇〇(作業名)における作業時間を〇%短縮する」
手段を検討する
設定したゴールを達成するために、最適な「見える化」の手段(ツール、システム、手法など)を検討します。
例えばデータ収集のために「デジタル現場帳票」や「IoTセンサー」の導入を検討したり、集計したデータを可視化するためにBIツールやダッシュボードを導入する等、考えられる手段を洗い出しましょう。
特に「現場帳票のデジタル化」は、見える化の要である「データ収集基盤」を構築するうえで非常に重要なポイントになるので、導入の推進方法を知りたい場合はPDF資料「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」もあわせてご覧ください。
また、作業手順の標準化手段としては動画マニュアルも有効手段です。製造業では技術伝承やカンコツの可視化を実現するために、動画マニュアルを導入している現場が徐々に増えています。製造業での具体的な動画マニュアル活用例については、以下の画像をクリックしてPDF資料「製造業における動画マニュアル活用事例集」もあわせてご覧ください。
運用・振り返りを行う
「見える化」の仕組みを構築したら、実際に運用を開始し、定期的に振り返りを行います。事前に立てた目標に対して問題が改善されているかどうか、定点観測を行いながら効果検証し、改善を繰り返していきます(PDCAサイクル)。
現場の意見を積極的に聞きながら、運用の軌道修正を行うことも重要です。もし目標に対して一定の成功が見られている場合は、さらに見える化の対象を広げ、現場全体の改善につなげていきましょう。
「工程・進捗」を見える化した製造業の事例とシステム
実際に「工程・進捗」の見える化に成功した企業事例をご紹介します。
アルミニウム表面処理を専門とする「株式会社日本電気化学工業所」は、長年、紙帳票でデータを管理していました。しかし、異常値の発見の遅れ、データ活用が進まない、承認作業の負荷が高い、といった課題を抱えていました。
そこで同社は、デジタル現場帳票「tebiki現場分析」を導入。これにより、製造工程における重要なパラメーター(温度など)をリアルタイムで確認できるようになり、異常の早期発見と迅速な対応が可能になりました。
例えば、現場に設置したディスプレイからダッシュボードで温度データのわずかな変化を捉え、配管の異常を早期に発見。大規模な故障や生産ライン停止という事態を未然に防ぐことができました。従来の紙帳票での管理では、このような微細な変化に気づくことは困難でした。
また、データの蓄積・分析が容易になったことで、長期的な視点での品質改善計画を立案できるようになりました。承認作業も効率化され、管理者はデスクトップ上で全記録を一目で確認。異常値は強調表示されるため、確認作業の時間を大幅に短縮できました。
同社が導入したデジタル現場帳票の詳しい機能や活用事例についてもっと知りたい方は、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析 サービス資料」もあわせてご覧ください。
また同社の詳しい事例は、以下の動画からご覧いただけます。現場の本格的な見える化を実現した企業事例を知ることで、具体的な導入イメージがつくようになるでしょう。
▼工場の「見える化」事例インタビュー▼
「技術・業務(人)」を見える化した製造業の事例とシステム
自動車部品や産業機械などの製造を手がける「大同工業株式会社」は、技術部門において、以下のような課題を抱えていました。
- 新人教育やマニュアル作成に工数がかかる
- トレーナーによって指導内容が異なり、業務品質にバラつきが出る
- 試験手順のわずかな違いから、ヒヤリハットや評価エラーが発生する
これらの課題を解決するため、同社は製造業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入。これまで文書化が難しかった、熟練技術者の持つ「コツ」や「ポイント」を動画で見える化できるようになりました。これにより、新人教育の効率が向上しただけでなく、ベテラン社員も含めた全部門の業務手順を再確認、標準化が実現できたのです。
結果、教育工数の8割削減。指導内容のバラつきもなくなり、業務品質が均一化されました。最終的にはマニュアル作成も内製化され、従来2時間かかっていたものが1時間以内で完了するようになったのです。
作成した動画マニュアルは、現場のタブレット端末で視聴できるようにし、QRコードを活用することで、必要な時に、必要なマニュアルをすぐに参照できる環境を整備。さらに、動画マニュアル作成の過程で、ベテラン社員の持つ暗黙知が形式知化され、部門全体の技術レベルの底上げに繋がりました。
技術やノウハウの見える化を実現した同社が導入した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場分析」の詳しい機能や活用事例は、以下の画像をクリックしてダウンロードできます。あわせてご覧ください。
まとめ:製造業・工場の見える化とは「工程」と「人」の可視化である
製造業の「見える化」とは、単にデータをグラフ化することではありません。生産に関わるあらゆる要素を可視化し、そこから得られた情報をもとに、継続的な改善活動を推進するための戦略的な取り組みです。
そして、その「見える化」とは「工程・進捗」と「技術・業務(人)」であると解説しました。
これら両方の側面から「見える化」に取り組むことで、製造業は、生産性向上、品質向上、コスト削減、納期短縮、そして従業員エンゲージメント向上といった、様々なメリットを享受できるのです。
しかし、「見える化」の取り組みは、一朝一夕に成果が出るものではありません。明確な目的設定、現場の理解と協力、そして継続的な改善活動が不可欠です。そのうえで、適切なツールを導入する必要があります。適切なツールとは以下2つです。
「tebiki現場分析」 は、現場帳票をデジタル化し、データ収集・分析を効率化。リアルタイムなデータに基づいた、迅速な意思決定をサポートします。「tebiki現場教育」 は、熟練工の技術やノウハウを動画で可視化し、技術伝承の促進、教育の効率化、業務の標準化を実現します。
こうした現場DXツールやシステムを活用することで、「見える化」の取り組みを加速させ、より大きな成果を上げることが可能になります。tebikiの詳しい機能や活用事例がまとめられたPDF資料は、以下のフォームよりダウンロードいただけます。ぜひ、本記事を参考に、「見える化」への第一歩を踏み出し、製造現場の改善、ひいては企業全体の成長に繋げていただければ幸いです。