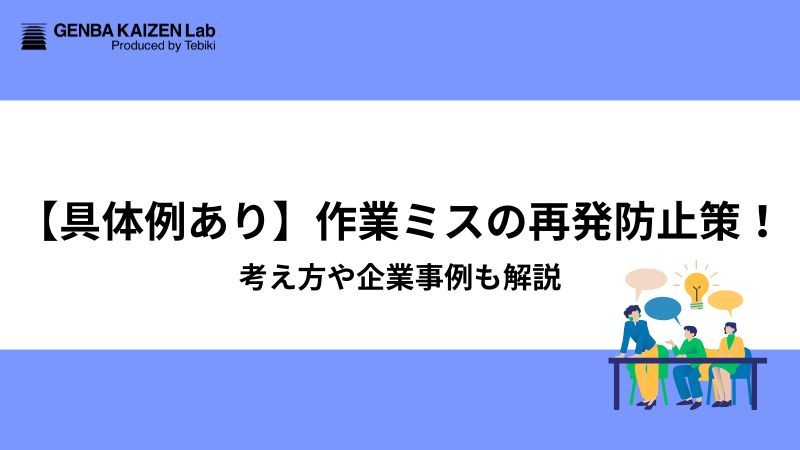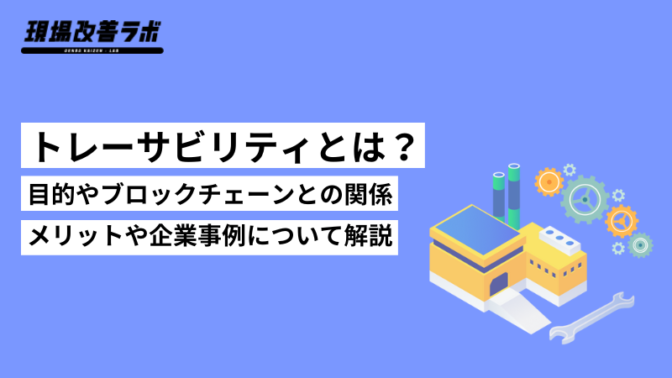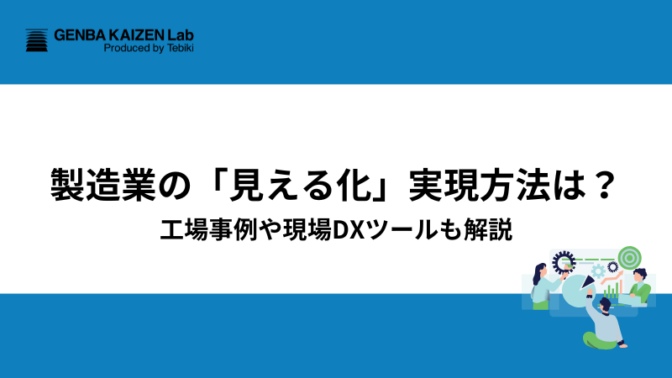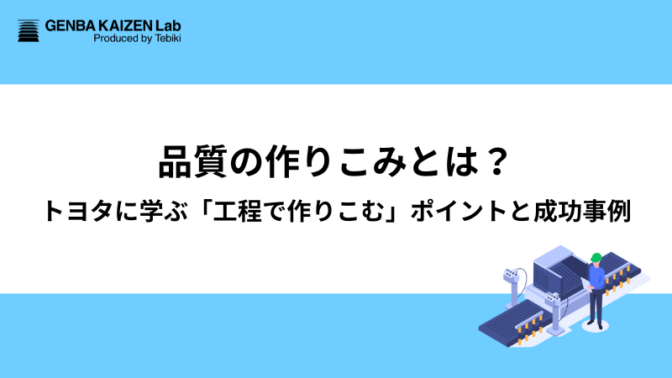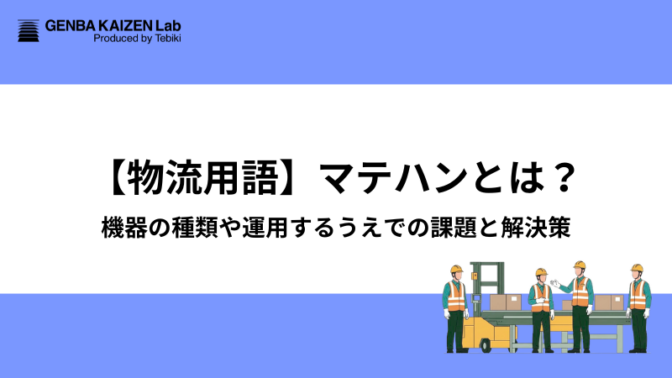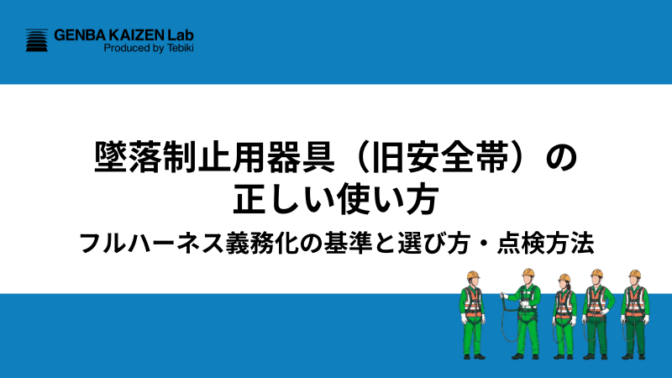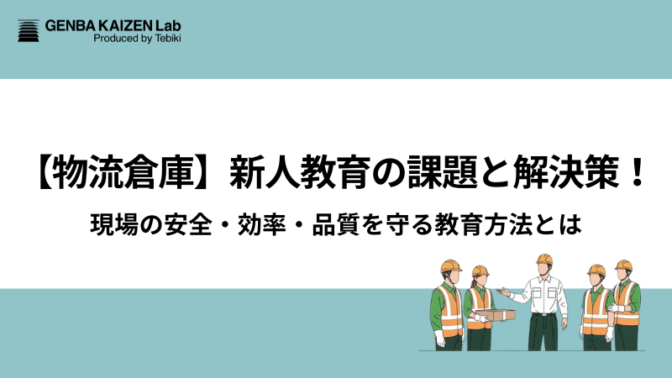製造業において、再発防止策は品質維持と安全確保の要です。本記事では、再発防止の定義と重要性、作業ミスが発生する6つの原因、再発防止策として5つの具体例を解説します。さらにチェックシートの活用やマニュアルの整備方法など、効果的な再発防止策もご紹介します。
再発防止策が現場に浸透しない多くの原因は、以下の3つに大別されます。
・場当たり的なOJT(その場しのぎや口頭指導)
・読まれないマニュアル(形骸化)
・進まない技術伝承(スキルのばらつき)
これらを解消する術として有効なのが「再発防止策を見える化する教育体制」であり、多くの現場で「動画による教育(マニュアル)」が導入されつつあります。動画マニュアルを通じた再発防止策の浸透や事例の詳細は、以下の資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』でまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』を見てみる
目次
【なぜ再発する…?】作業ミスやトラブルを防止できない原因
作業ミスやトラブルを防止するための対策を講じていたとしても、再発を完全に防ぐことは困難です。ここでは、作業ミスが発生してしまう原因について詳しく解説していきます。
教育内容の不統一による作業のばらつき
従業員ごとの教育内容が統一されておらず、正しい手順や基準で作業されていないことは、ミス再発の大きな原因の1つです。
このような作業品質のばらつきは、OJTをはじめとした「新人教育のやり方」に問題が潜んでいることが多いです。
- OJTの担当者ごとに伝える内容が異なっている
- 技術やカンコツの言語化ができていない
- 結果、教育を受ける側によって解釈が異なる
こうした要因がミスを招きます。また、一度慣れてしまった作業のやり方や手順については、再教育を実施したとしても中々改善することは難しいため、繰り返し同じようなミスが発生してしまうのです。
現場改善ラボが会員に対して実施した現場教育に関するアンケート(N数=156人)でも、「担当者ごとの作業内容のばらつき」は教育課題でトップを占めています。
【教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例】より抜粋
現場のアンケート結果をもとにした、「教育のばらつきを解消するポイント」も資料内で紹介しています。教育内容のばらつき改善に成功した企業の好事例も掲載しているので、下のリンクをクリックしてぜひ資料をご覧ください。
>>「教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例(PDF資料)」を見てみる
技能伝承が進んでいない
業務が標準化されていないことで、従業員ごとの経験則や独自のやり方で作業が行われていて、技能伝承が進んでいない点も作業ミスが多くなる原因の1つです。技能伝承が正しく行われないことによって、作業の属人化が蔓延してしまう悪循環を生み出します。
また、従業員が増えるにつれてそれぞれのやり方が生まれるので、ミスの温床にもなるでしょう。一例として、冷凍食品などの製造・販売を手掛ける「テーブルマーク株式会社」でも、標準化されていないことで以下のような課題を抱えていました。
「現場従業員の意識統一」や「技能伝承」といった点でも課題を感じておりました。たとえば、出来上がった製品を確認するときに、人によって見ているところが違ったり、見落としているポイントがあったりというような、従業員による差が生まれているところがありました。
同社が抱えていた課題や課題に対する取り組みについて詳しく知りたい方は、インタビュー記事「属人化業務の指導工数を83%削減!標準化教育により安心安全な食品を提供」をご覧ください。
>>技術・技能伝承の進め方~伝承を阻害する5つの誤解とその解決策~を見てみる
作業の慣れや確認不足
作業に慣れることも、ミスが発生する原因となるので注意しましょう。長期間同じ作業を続けると作業者は次第に緊張感を失い、注意力が低下することがあります。
「慣れ」によるミスは、新人 / ベテラン関係なくだれでも発生することがあり、普段では考えられないようなミスになることもおかしくありません。また、本来は作業終了時に「確認」する工程が入る場合でも、慣れや慢心によって確認が行われずに、そこから重大なミスに発展することも考えられます。
これらの不安全行動は、単なる注意喚起や直接指導ではゼロにできません。不安全行動が根本的に起きない「仕組み作り」が重要ですが、行動科学の観点から具体的な対策が解説されている「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」を参考にすると、本質的な安全対策のヒントが得られるはずです。あわせて参考にしてみてください。
>>「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」を見てみる
疲労やストレスによる集中力低下
長時間の労働や過度のストレスがかかる環境では、身体的・精神的な疲労が蓄積し、ミスを誘発します。
たとえば、連続した残業や休息の不足のため、判断力や反応速度が鈍くなり、誤った操作や見落としが発生することがあります。
作業者間のコミュニケーション不足
コミュニケーション不足も作業ミスの原因となります。たとえば、作業指示が全員に伝わっていないことや、変更点が共有されていないことで、誤った作業が行われる場合があります。
【具体例あり】作業ミスの再発防止を実現する手段
ここからは作業ミスの再発防止を実現する具体的な手段について紹介していきます。ソフト面(人材・仕組み)とハード面(設備や機械)それぞれのアプローチで有効な手段を紹介するので、自社の状況に合わせて最適な手段を選択してみてください。
※再発防止策が現場に浸透しない多くの原因は、以下の3つに大別されます。
・場当たり的なOJT(その場しのぎや口頭指導)
・読まれないマニュアル(形骸化)
・進まない技術伝承(スキルのばらつき)
これらを解消する術として有効なのが「再発防止策を見える化する教育体制」であり、多くの現場で「動画による教育(マニュアル)」が導入されつつあります。動画マニュアルを通じた再発防止策の浸透や事例の詳細は、以下の資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』でまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』を見てみる
ソフト面(人材・仕組み)で有効な再発防止策
人材への教育や仕組みなどのソフト面での有効は再発防止策は以下があげられます。
- 作業手順書/マニュアルの整備
- 指差呼称やWチェックの強化
- 誰が教えても同じ教育水準になる体制の構築
- 従業員のスキルを把握し、人材配置を最適化
- なぜなぜ分析でミスが発生する原因を追求
- 慣れや確認不足、思い込みがあってもミスが発生しない仕組みの構築(フールプルーフ)
作業手順書 / マニュアルの整備
作業品質のばらつきや手順不遵守などが頻繁に発生している場合、まず講じるべきは作業手順書 / マニュアルの整備です。マニュアルを整備し直すことで、従業員が共通の手順や基準、ルールに基づいて作業に取り組めるので、作業ミスやばらつきの発生を低減できます。
一方で、マニュアル整備の重要性を理解しているものの、通常業務と比べて優先度が低いことで中々着手できない場合もあるはずです。これは、テキストベースでマニュアルで作成していることにより、手順やルールを一から十まで書き込まなければならず、整備するハードルが非常に高くなっていることが原因です。
このような課題を解消する上で、テキストや画像がメインの文書マニュアルと比べて、実際の作業風景を撮影してかんたんな編集作業のみでマニュアルを整備できる「動画マニュアル」が有効です。
実際に作業をしている風景を見れるので、視聴者ごとの認識の相違が発生を低減することが可能です。実際に「児玉化学工業株式会社」では、以下のような一目で作業内容がわかる動画マニュアルを整備しています。
※「tebiki現場教育」を活用して作成されています。
動画マニュアルと聞くと作成するハードルが高いと感じる方が多いかもしれませんが、同社で導入されている「tebiki現場教育」は、導入後2年で9,000本以上のマニュアルを作成している企業(東急リゾーツ&ステイ社の事例より)もあり、動画編集経験がない方でも簡単に作成できるのが魅力です。tebiki現場教育の詳しいサービス内容や導入企業の事例、導入メリットなどは、以下のリンクをクリックしてサービス資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料(PDF資料)を見てみる
指差呼称やWチェックの強化
確認や注意不足などのヒューマンエラーを起因とする作業ミスには、Wチェック体制の構築や指差呼称が有効です。
作業完了時に別の従業員によるチェックを入れることで、作業の抜け漏れを防ぎ、ミスが発生するリスクを防止することができます。従業員を経験年数が長く、習熟度が高いベテラン従業員にWチェックを担当してもらうことでよりミスの防止が見込めるでしょう。
また、チェックする際には、見る / 指差す / 呼称するという動作を組み合わせる「指差呼称」を実施しましょう。意識レベルを上げられ、緊張感や集中力を高める効果も期待できるため、作業ミスを見過ごすリスクの防止につながります。
Wチェックや指差呼称は有効ですが、それが形骸化すると意味がありません。作業ミスが繰り返される「不安全行動」を行動科学の力で防止する方法がこちらです。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
指差呼称については、以下の記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
関連記事:【事例あり】指差呼称とは?効果はある?正しいやり方や定着させる教育方法
誰が教えても同じ教育水準になる体制の構築
教育の担当者によって、教育内容や伝え方などに微妙な違いが発生してしまうことにより、作業ミスや品質の低下につながる可能性が考えられます。
このようなリスクを防ぐには、誰が教えても教育内容にばらつきが発生しない教育体制の構築が必要です。
教育水準を一定にする手段として、実際の作業風景や動きを一目で見れてある程度の作業内容を理解できる動画マニュアルは非常に有効です。1から10までの説明が不要であり、動画を視聴してもらうだけで作業内容を理解してもらえるため、OJTの負担も最小限に抑えられます。
従業員ごとの業務習熟度も一定に保てることで、作業ミスの発生率も低減できるでしょう。なお、現場で実際にどのような動画マニュアルが活用されているのか、どのような効果を得られているのかなどをまとめたPDF資料「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集」もご用意しています。下のリンクをクリックして資料をご覧ください。
>>「実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集(PDF資料)」を見てみる
従業員のスキルを把握し、人材配置を最適化
従業員ごとに保有しているスキルや作業への習熟度は異なるため、それぞれの従業員の特性を理解した上で、適切に人材を配置するのが重要です。
人材配置を最適化する上で必要なのが、従業員ごとの保有スキルを可視化できるスキルマップです。スキルマップを活用することによって、以下のような効果を得られます。
- スキルを持たない作業者が現場に入ることを防止できる
- 「誰に・どのスキル」が不足しているかが明確になり、最適なトレーニングを行える
- スキルの獲得基準が明確になることで、平等な評価ができモチベーションアップにつながる
スキルマップの作り方や具体的な活用方法などについては、関連記事「【無料Excelテンプレ付】スキルマップの作り方!トヨタでの活用例や評価基準」で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
なお、人材配置を最適化する上で必要な従業員スキルを可視化には、スキルマップの活用が有効です。従業員視点でも、どのスキルを取得すると評価につながるか?という点が可視化されます。
とはいえ、スキルマップの運用が続かず形骸化している製造現場は少なくありません。紙による管理が煩雑で、気が付けば最新状態に更新されていないというケースが多いです。そこで推奨したいのが、「クラウド型スキルマップ」の導入です。
例えば、製造現場に特化したクラウド型スキルマップ「tebiki現場教育」では、下図のように「従業員ごとのスキル習得状況」を可視化します。

【「動画マニュアルが紐づくクラウド型スキルマップ – tebiki現場教育」より抜粋】
tebiki現場教育の詳細機能や活用事例について詳しく知りたい方は、以下のPDF資料もあわせてご覧いただくと、tebikiを現場でどのように活用できるのか・どのように稼働率向上に貢献するのかが具体的にイメージできます。
>>>PDF資料「動画マニュアルが紐づくクラウド型スキルマップ『tebiki現場教育』」を見てみる
なぜなぜ分析でミスが発生する原因を追求
作業ミスの再発防止をする上では、ミスが発生する根本となる原因を明確に追求するのが重要です。根本となる原因を突き止めて対策しない限り、似たようなミスを防止することはできません。
例えば、工場の製造ラインで部品の取り付けミスがあった際に講じられる対策は、注意換気のポスターを掲示、ダブルチェックの導入などであり、これらはあくまでも「その場しのぎの対策」です。ミスが発生した根本となる原因(作業手順が複雑、照明が暗いなど)が解決しない限りミスは繰り返されます。
このようなミスの根本となる原因を追求する上で有効なのが、トヨタ自動車で生み出された「なぜなぜ分析」です。ミスに対して5回の「なぜ」を繰り返すことで、課題の根本を見つけることができます。
なぜなぜ分析について詳しく知りたい方は、トヨタ自動車の社内で「なぜなぜ分析」の研修講師を担当していた専門家による解説をまとめた資料をご覧ください。例題を交えながら成果が上がるなぜなぜ分析の実践方法などを解説しているので、本格的な「なぜなぜ分析の進め方」を理解できるはずです。
>>【事例で解説】(解説動画あり)トヨタ流「なぜなぜ分析」の実践方法とポイント(PDF資料)を見てみる
慣れや確認不足、思い込みがあってもミスが発生しない仕組みの構築(フールプルーフ)
慣れや確認不足、思い込みなど作業ミスの主な原因があったとしても、それらをきっかけにミス(ヒューマンエラー)につながらないような仕組みを整備して構築するのも有効な手段の1つです。
このように、そもそもミスが発生しないようにするもしくは、仕組みでミスが大きくならないようにすることを「フールプルーフ」と呼びます。例えば、誤った操作をしようとした際に、そもそも操作自体ができないようにすることであったり、危険な状態になると警告音を発するようにしたりするなどがあげられます。
人に由来した作業ミスを防止する上での具体的な対策方法、フールプルーフとヒューマンエラーの関係性などについては、以下のPDF資料で詳しく解説しています。再発防止に向けたヒントが盛り込まれた内容になっていますので、下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法(PDF資料)」を見てみる
ハード面(設備や機械)で有効な再発防止策
設備や機械などのハード面での有効な再発防止策としては、以下のようなものがあげられます。
5S活動をはじめとした、作業環境の改善
「作業で利用する際に必要な道具が見つからない」「ものが多くて十分な導線を確保できない」など、作業をする環境が整備されていないことでミスが多発している場合には、職場環境の改善に着手すべきです。
職場環境を改善する有名な手法として、トヨタ自動車で生まれた「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動」が有効です。単に作業環境をきれいにするだけではなく、3M(ムリ・ムダ・ムラ)を排除することも期待できます。ムダな動きが排除されている状態が実現し、作業工程をシンプルに改善できるため、複雑な作業が不要になってミスの発生を防止することもできるでしょう。
5Sの有効性は理解していても、「活動が定着しない」「いつの間にか元通り」という現場は少なくありません。
精神論ではなく、5S・3定を組織の「仕組み」として浸透させるためのポイントを、以下の資料で解説します。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」を見てみる
作業ミスを蓄積する仕組みやシステムの整備
作業ミスが発生した際、いつ・どこで・どんな作業をして・どのようなミスが発生したのかなど、発生したミスを蓄積し、共有する仕組みを構築するのも有効です。
ミスが発生する仕組みや原因をナレッジやノウハウとして蓄積し、適宜共有することによって、従業員の安全や品質に対しての意識が高まります。発生したミスを蓄積するのにはナレッジマネジメントツールの活用が有効です。
ミスが発生しやすい作業を機械やAIで自動化
作業内容によってはどれだけ対策をしたとしてもミスを防止することが難しい場合もあるため、機械やAI、ロボットなどでの自動化も検討してみましょう。
人の手が介在しないため、ヒューマンエラーが発生することがなく、作業スピードも人と比べて格段に早く生産性の向上も見込めます。また、省人化により、人件費の削減にもつながります。
「策」だけではNG!確固たる再発防止に必要な考え方
再発防止を実現するためには「策」だけを講じても思うような成果を得られる可能性は低いため、徹底させるためのポイントを踏まえる必要があります。具体的な方法は以下のとおりです。
- リーダーやマネージャーが積極的に取り組む
- ミスをどの程度防止できたのかを可視化する
再発防止策が現場に浸透しない多くの原因は、以下の3つに大別されます。
・場当たり的なOJT(その場しのぎや口頭指導)
・読まれないマニュアル(形骸化)
・進まない技術伝承(スキルのばらつき)
これらを解消する術として有効なのが「再発防止策を見える化する教育体制」であり、多くの現場で「動画による教育(マニュアル)」が導入されつつあります。動画マニュアルを通じた再発防止策の浸透や事例の詳細は、以下の資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』でまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』を見てみる
リーダーやマネージャーが積極的に取り組む
トップダウンで再発防止策を従業員に実施させても、その重要性が伝わらないため、早い段階で形骸化する可能性が非常に高いです。そのため、リーダーやマネージャーが積極的に再発防止の対策に取り組み、全員でミスを防ぐ意識を浸透させるようにしましょう。
リーダー層が積極的に再発防止の取り組みを実践し模範を示すことで、従業員の意識を高め、取り組みの一貫性を保てます。
ミスをどの程度防止できたのかを可視化する
実際に再発防止の対策を実施してみて、取り組みによってどの程度の成果(ミスの防止)ができたのかを可視化し、従業員に周知するのも有効です。
例えば、以前までは月に100件発生していた作業ミスが30件まで減った場合、従業員に周知すれば日頃の再発防止策への取り組みによる成果を実感でき、モチベーション向上にもつながります。再発防止策の進捗を定期的にモニタリングし、適切なフィードバックを心がけましょう。
その中で、従業員ごとに良い取り組みがあれば、朝礼や終礼、掲示物などでその取り組みを評価するのも有効です。
対策の効果を可視化し改善に繋げることは、再発防止を確実にするために不可欠です。この一連のプロセスを、品質不良の真因を断つために体系化したのが、トヨタ式の「QCストーリー」です。
>>トヨタ式QCストーリーを通じた、品質不良の真因を断つ再発防止策を見てみる
作業ミスの再発防止を実現している企業の好事例
ここでは、作業ミスの再発防止を実現している企業の好事例を紹介していきます。
以下の資料も併せてご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」導入事例集を見てみる
株式会社神戸製鋼所:OJT前の動画教育によって再発防止を実現
素材系事業、機械系事業、電力事業を展開する日本の大手製造企業である株式会社神戸製鋼所では、紙の手順書+OJTによる教育を実施してましたが、教育者ごとの教え方の違いや教育される側の受け取り方の違いによって、作業習熟度に差が発生して作業品質がばらつく課題を抱えていました。
そこで、紙+OJTの教育から作業内容のニュアンスや動きが伝わりやすい「動画マニュアル(tebiki現場教育)」を活用した教育に切り替えました。結果として、教育者による教え方のバラツキが無くなるため、作業手順の間違いや理解不足を低減させることにつながっており、ミスの再発を防止する環境の構築が進んでいます。
同社の詳しい事例を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
インタビュー記事:動画を活用した現場の人材教育効率化と作業標準化
上松電子株式会社:動画による教育の繰り返しによって再発防止を実現
様々な自動車部品の製造をしている上松電子株式会社では、「品質」を事業における最優先事項として捉えており、経営において欠かせないテーマとして考えています。
品質不良が発生する原因の4割が教育不足に起因しており、特に塗装工程の不良・作業ミスが繰り返される状況に陥っていました。そこで、作業ミスをなくし、教育方法を改善する目的で動画マニュアルの作成&従業員教育もできる「tebiki現場教育」を導入。
塗装ライン専用の動画マニュアルを作成し、見逃しが多く発生していた作業者には動画マニュアルで繰り返し教育を行い、手順通りの作業ができるよう徹底したところ、500ppm※を5週間かけて一時的に撲滅することに成功しています。
同社の詳しい事例を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
インタビュー記事:「教えたつもり」をなくし、塗装工程の不良見逃し率を大幅に削減
※PPM=Parts Per Millionの略。製品100万個あたりの不良品の数を示す単位
再発防止策がうまくいっている企業の共通点
「作業ミスの再発防止を実現している企業の好事例」で紹介した企業では、動画マニュアルを活用した独自のアプローチによって、従業員教育を実施して作業ミスの再発を防止していることがわかります。
2社の事例はいずれも製造業でしたが、他業種の物流企業「ASKUL LOGIST株式会社」でも、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」が導入されており、以下のように作業の標準化によって再発防止を実現しています。
実際に動画マニュアルで教育を行ってみると、従来の教育だけでは受け手側の解釈で理解がバラついてしまう中でも、うまく作業の標準化を進められることが効果として大きいです。文字ベースの紙マニュアルだけで見てもらうよりも絵や写真などビジュアルも使うことで分かりやすいですし、それが動画になるとより分かりやすくなりますよね。
様々な業界での導入実績があるtebiki現場教育について、搭載されている機能や詳しい特徴、導入時のサポート内容などについて詳しく知りたい方は、tebikiのサービス資料もご覧ください。以下をクリックすると資料をご覧頂けます。
まとめ
作業ミスの再発を防止するうえでは、従業員への教育による品質や安全への意識の向上、ミスが繰り返されない仕組みの構築などが必要です。自社でどのようなミスが繰り返されているのか、原因を追求してそれにどのような対策が必要なのかを今一度考えてみましょう。
なお、この記事で紹介した「tebiki現場教育」は、動画マニュアルによる新たなアプローチによる教育によって、作業の標準化を実現し作業のミスを防止することにつながります。
「tebiki現場教育」についてより詳しい情報を知りたい方は、以下をクリックしてサービス資料をご覧ください。