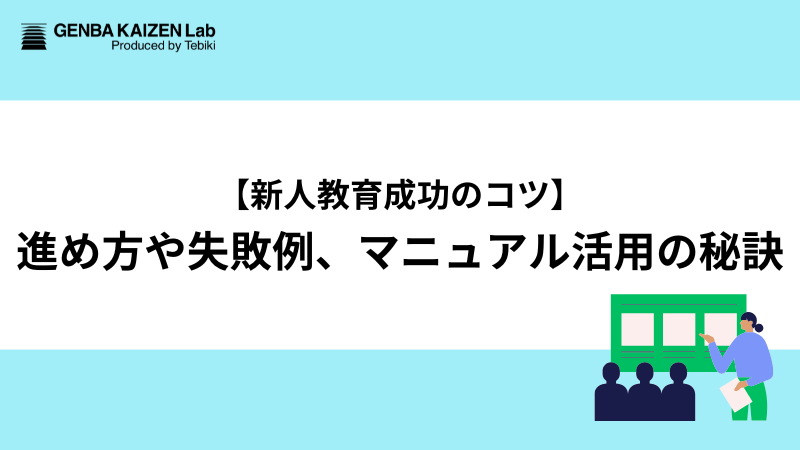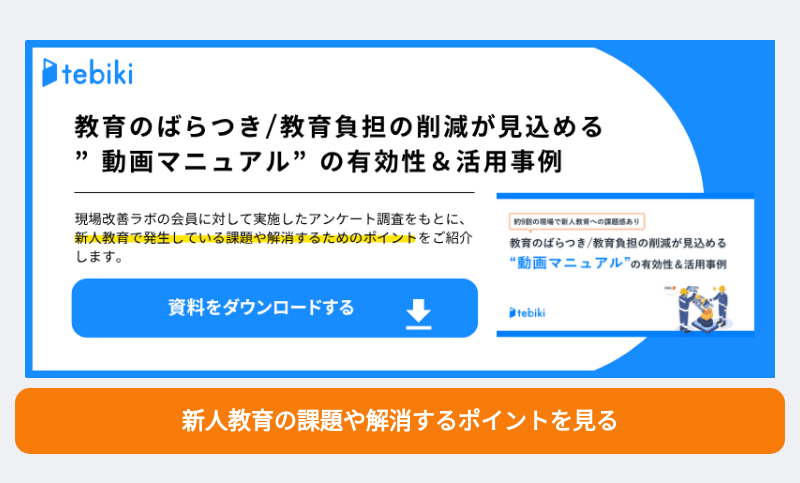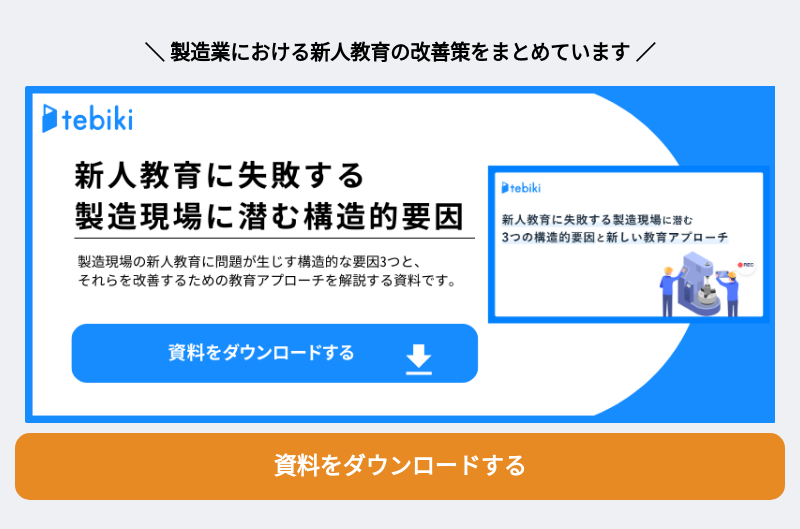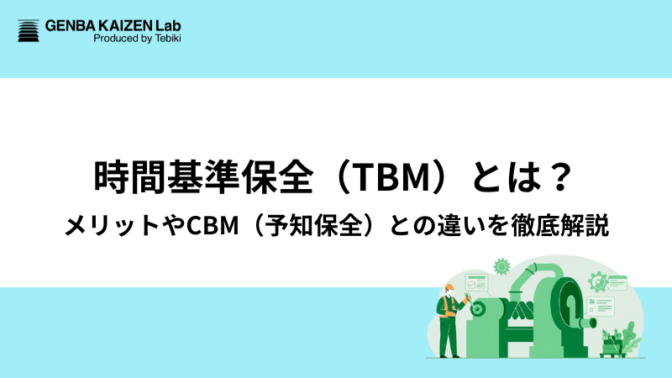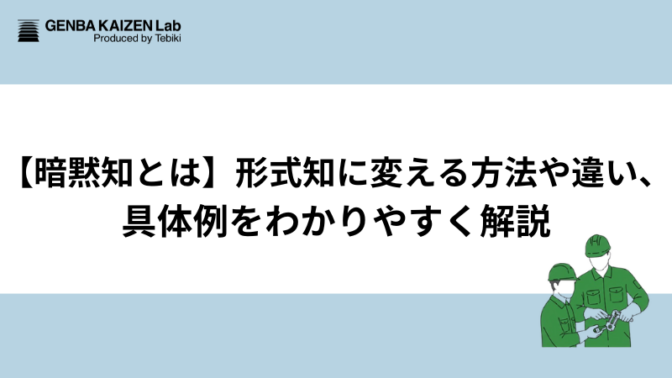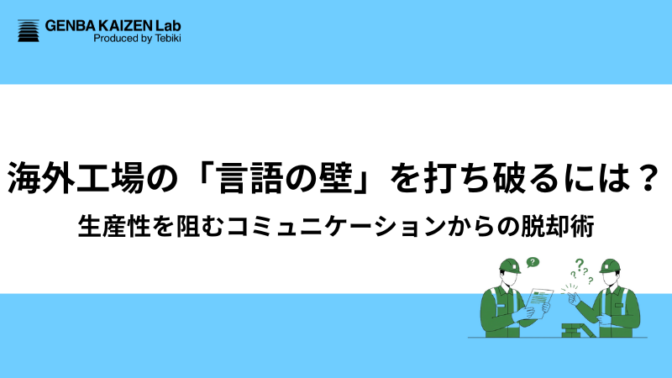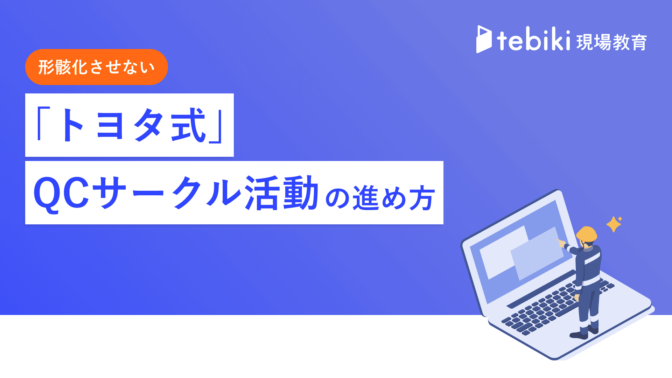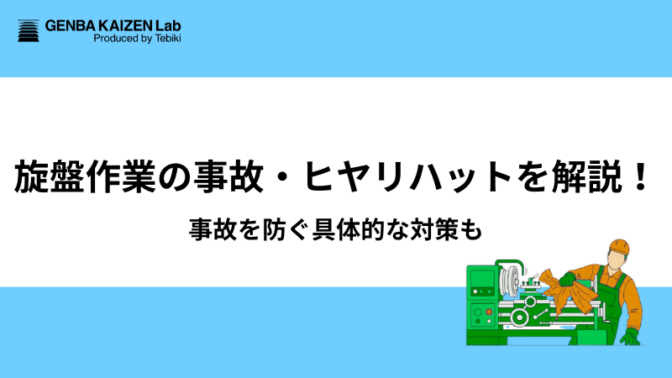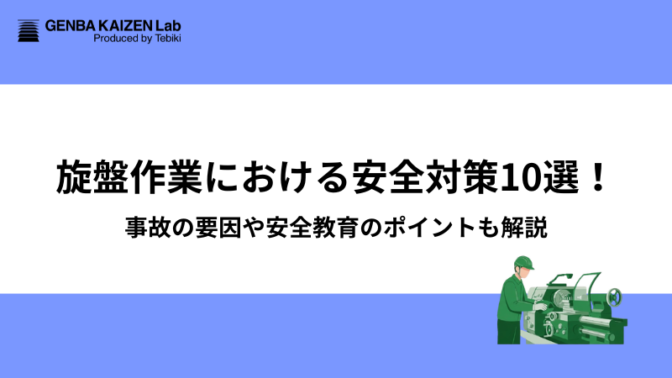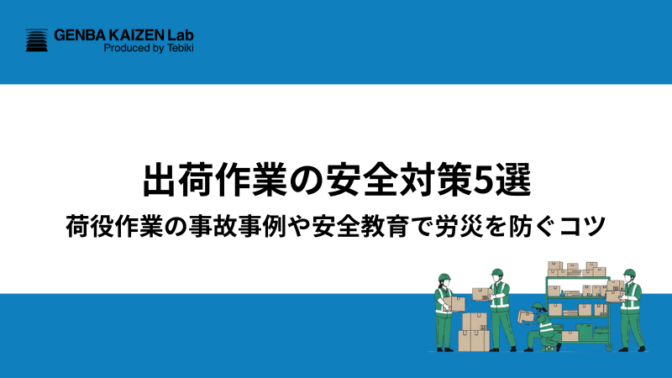かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
新人教育は即戦力となる従業員の育成だけでなく、企業文化の形成や業績向上のために欠かせない取り組みです。しかし、明確な正解があるわけではないため、「新人の教育に失敗しないコツを知りたい」と考えている方も多いはずです。
この記事では、全業種に共通する新人教育のコツや進め方などを紹介します。
なお、以下の資料では独自のアンケート調査をもとに、現場教育のリアルな実態や抱えている課題を踏まえて、新人教育を成功に導くコツを紹介しています。下の画像をクリックして、資料をご覧ください。
目次
新人教育を行う目的
新人教育の主な目的は新入社員を企業文化に馴染ませ、業務遂行に必要なスキルと知識を獲得させることにあります。
新人教育により新人は自信を持って業務を遂行できるようになり、早期に会社の戦力となるでしょう。製造業の例では新人に対して製品の品質基準や製造プロセス、安全規則を教育することで製造ラインの効率化と事故の防止につながります。
新人教育の重要性や手法については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事:新人教育の目的と重要性とは?効果的な教育方法や実際の取組事例を紹介
全業界に共通する新人教育を行う際のコツ
新人教育を実施する場合、特定の業界だけではなく全ての業界に共通した、新人教育のコツがあります。ここでは、特に意識しておきたいポイントを紹介していきます。
誰でもわかるような言葉で伝える
新人に対して、業界ごとに特有の専門用語や社内だけでしか伝わらない言葉などは利用を避けたほうが良いでしょう。意図が十分に伝わりきらずに、教育の効果を得られない可能性があります。
できるだけ平易な言葉遣いで、一般的な言葉を使用し、徐々に専門用語に触れる形でグラデーションをもたせるのがポイントです。どうしても専門用語を使用する必要がある場合には、用語集を用意して新人の負担を減らすなどの取り組みが有効です。
心理的安全性を確保できる環境を作る
会社に入りたての新人は、環境や人に馴染めていないことが多く、たくさんの不安や疑問を抱えています。
新人によっては、「質問したくても遠慮してしまう」「誰に聞いてよいのかわからない」などの状況に陥っている可能性も考えられます。エドモンドソンの「4つの心理的安全性を損なう要因と特徴行動」によると、心理的安全性が低い現場に共通しているのは以下の4点です。
- 無知だと思われる不安
- 無能だと思われる不安
- 邪魔をしていると思われる不安
- ネガティブだと思われる不安
このような状況では、教育を通した学びが少なくなってしまうため、できるだけ負担を解消できるように1on1や積極的なコミュニケーションを通じて、心理的安全性を確保できる環境を作るように心がけましょう。
考える時間を与える
新人に考える時間を与えることで、自ら問題を解決する力を養うことも必要です。即座に答えを与える教育をしてしまうと新人は自ら考えることをやめてしまい、長期的に成長することができなくなってしまいます。
例として「この作業をさらに効率的にするにはどうすればいいか?」といった問題提起を通じて、新人が自ら考えたうえで改善策を提案させることが有効です。
新人のスキルやキャリアプランを考慮する
新人ごとに性格や特性、キャリア志向などは異なるため、それぞれのスキルやキャリアプランを考慮した上で、教育を進めていくことが大切です。全ての新人に同一の観点で教育を実施しても、新人の個性を伸ばすという視点では最適ではないかもしれません。
そのため、定期的な1on1や適切なコミュニケーションを通じて、教育対象の新人社員をしっかりと理解するのが重要です。業務進捗はもちろん、「今後どのようなキャリアを形成していきたいか」など中長期的な視点での質問を通じて、新人社員を理解できるようにしましょう。
指導内容に一貫性をもたせる
右も左もわからない新人に対して、指導の内容が毎回異なると不安や負担をかけてしまいます。誤った認識で業務に望んでしまい、業務効率の悪化や大きなミスなどにつながる可能性も考えられるので注意が必要です。
そのため、指導する内容には一貫性を持たせるのが大切です。指導担当者ごとでのブレを無くすためにも、認識を統一しておくことも心がけましょう。もし指導方針の転換などによって、発言が変わる場合には背景や経緯を説明するなど、学ぶ側が納得感を得られるようにするのが大切です。
トレーナごとの指導内容のバラつきを統一するため、大同工業株式会社では、OJTなど新人教育の内容を動画マニュアル化し、指導内容を統一化しつつ教育工数の効率化を実現しています。同社の具体的な取り組み内容は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。
目的・理由も合わせて説明する
新人教育では「何をするか」だけでなく「なぜそれをするのか」を明確に伝えることが重要です。作業の背後にある目的や理由を理解することで、新人は単に作業をするだけではなく、業務が企業にどのように貢献しているかを認識できるためです。
たとえば業務を教える際に「この業務を行うことで顧客満足度を高め、企業の信頼性を確立する」という目的や理由を伝えることが重要です。目的と理由を伝えることにより、新人は業務を単なるルーティーンではなく、企業の成功につながる活動として捉えるようになります。
指摘・注意する際は伝え方に気をつける
新人への指摘や注意をする際、伝え方には注意しましょう。頭ごなしに指摘をすると、新人が萎縮してしまいモチベーションが低下して学習意欲が損なわれる可能性があります。また、人格を否定したり、他の同期と比較するなどは絶対に避けるべきです。
指摘する際には、「指摘する理由や背景を添える」「時間をかけず端的に伝える」「フォローの言葉を添える」を心懸けましょう。ポジティブなフィードバックと指摘をバランス良く行うことで、新人は自己肯定感を持ちながら成長できるはずです。
わかりやすいマニュアルを活用する
新人教育では、社会人としての基本的なマナー・ルールはもちろん、社内規則や業務に関する様々なことなどを一気にインプットしなければならず、覚えることがとても多いです。
簡易的な資料や口頭ベースのみの説明では、全てを理解することはできないため、新人教育を対象としたわかりやすいマニュアルを作成しましょう。マニュアルがあることで、繰り返し学べるので自主的な学習を推進できます。
なお、マニュアル=紙のイメージが強いかもしれませんが、マニュアル作成に動画を活用する動きは業界を限定せずに多くなっています。以下の資料では、新人教育に動画マニュアルを活用している企業事例、新人教育への有効性などを体系的に学ぶことができます。新人教育を成功させるコツを掴むヒントになるはずですので、下の画像をクリックして資料をご覧ください。
動画マニュアルを活用した新人教育の成功事例
ここでは、新人教育に動画マニュアルを活用している企業の好事例を紹介していきます。各社ごとにどのような課題・導入効果を得られたのかチェックしてみてください。
動画マニュアルに置き換え、教育工数をほぼ0に削減!| ロイヤル株式会社
ロイヤルグループ向けの袋入りレストラン用商品や機内食、容器商品などを製造しているロイヤル株式会社。同社では、タイミーを始め短期スタッフの数が増加しており、多い日で1日50名もの新人を受け入れが発生し、現場に教育の負担が集中する課題を抱えていました。
そこで動画マニュアルを導入し、短期スタッフの教育に動画を活用することで、社員からの説明時間を最小限に抑え、教育担当者の負担削減に成功しています。また、新人全員が同じ動画を視聴するため、教育のムラ解消にも実現し、属人化していた作業を別の担当者でも対応できるようになる効果も実感しています。
同社の事例を詳しく紹介しているインタビュー記事は「1日最大50名勤務するアルバイトの入場教育を動画マニュアルに置き換え、教育工数をほぼ0に削減!」をご覧ください。
新人教育時間を3,700時間削減|株式会社GEEKLY
IT・WEB・ゲーム業界に特化した人材紹介事業に従事している株式会社GEEKLY。同社では、従来のOJT教育において、トレーナーごとにバラつきがあり、新人社員の理解度に差が生じる、トレーナーへの負担が大きいという2点の課題がありました。トレーナーは1ヶ月あたり50時間ほど教育に時間がかかっていたそうです。
この2点の課題を解決するために、動画マニュアルを導入。OJT教育の7割近くを動画マニュアルに置き換え、トレーナー教育工数を削減することに成功しており、年間の時間に置き換えると約3,700時間にも及び、教育工数やコスト削減に大きく貢献しています。
同社の事例を詳しく紹介しているインタビュー記事は「年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!」をご覧ください。
新人教育には動画マニュアルの活用が効果的な理由
紙のマニュアルやOJTと比べて様々なメリットがあるため、新人教育に動画を活用している企業は増加している傾向です。ここでは、新人側・教育者側それぞれのメリットを具体的に紹介していきます。
新人側のメリット
教育を受ける側である新人社員にとって、動画マニュアルを活用するメリットは以下の通りです。
- テキストベースのマニュアルと比べて視覚的に学べる
- 詳細な動きや微妙なニュアンスを汲み取れる
- 視聴デバイスがあれば好きな時間に繰り返し学習できる
- 紙と比べて動画を視聴するハードルが低く、自発的に学べる
テキストと比べて動画と音声で学べるため、紙と比べて内容が分かりやすく、教育の負担を軽減できるのが特徴です。新人社員は覚えることが多いため、紙で学ぶと膨大な量になりますが、動画であれば気持ち的な負担も少なくなります。
また、昨今では動画のコンテンツを視聴する頻度も多いため、動画であれば視聴するハードルが低くなるのも、学ぶ新人にとってメリットと言えるでしょう。
教育者側のメリット
マニュアルの動画化は、新人だけではなく、教育者側にも様々なメリットがあります。
- OJTを動画に置き換えられるので教育工数を削減できる
- 紙と比べて動画を取るだけでかんたんにマニュアルを作成できる
- 改訂・更新に工数がかからない
- クラウド上に保管できるので管理工数がかからない
- 新人社員の自発的な学習を促進できる
「ロイヤル株式会社の事例」でも紹介したように、これまで担当者が行っていたOJTを動画に置き換えられるので、教育担当者の工数を大幅に削減できるのがメリットです。逐一説明をしなくても、「〇〇の動画を見てください」と指示をするだけで済むので、不要なコミュニケーションコストがかかりません。
また、紙の場合には、マニュアルが増えるごとに膨大な量になり、どこに求めているマニュアルがあるのか把握するのが困難です。一方で、動画で作成することで、クラウド上にマニュアルを保管でき、キーワードで検索をすれば必要な情報にかんたんにアクセスできます。
動画マニュアルの活用を検討している方は、動画マニュアルを活用するメリットや効果、作成時に押さえておきたいポイントなどをまとめた「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」もご覧ください。
なお、動画マニュアルの導入を検討している方には、企業事例でも紹介した「tebiki現場教育」がおすすめです。tebiki現場教育は、動画内の音声を認識して自動で字幕を生成できるので、スマートフォンやタブレットなどで新人教育の様子を撮影するだけでかんたんにマニュアルを作成できます。
次の見出しでは、tebii現場教育ならではのメリットを詳しく紹介していきます。
新人教育を最も効果的に進める「tebiki現場教育」
動画と聞くと「編集が難しそう…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、tebiki現場教育では、教育担当者の負担を軽減し、新人教育を効果的に進められる様々な機能が搭載されています。
- 映像編集未経験者でも「かんたん」に使える編集画面
- 音声読み取りによる字幕の自動生成機能
- 字幕を100ヶ国以上の言語へ瞬時に自動翻訳
- 一部言語は字幕の読み上げ機能に対応
- テスト機能やレポート機能による理解度・学習進捗の可視化
- スキルマップなどスキル管理機能による教育計画と実行
- 半永久的に続く専属サポート
かんたんで効率的にマニュアルを作成することができ、翻訳機能によって外国人従業員にも対応可能です。また、テスト機能やレポート機能の活用で、学習進捗の可視化もできます。
tebiki現場教育の詳しい機能やサービス内容を知りたい方は、「かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」」の資料もご覧ください。
失敗しない!新人教育の進め方
ここでは、新人教育の進め方について紹介していきます。どのような点を踏まえて教育を進めて行けばよいのかのコツもあわせて紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
新人教育の全体像となる教育計画を作成する
どれくらいの期間でどのような内容を教えるのかなど、新人教育の全体像となる教育計画を作成しましょう。場当たり的な教育を行っても良い学びは得られずに、新人の成長につながりません。
新人教育の計画を立てる際には、「組織の理想的な姿」「現状の社内状況を把握」「求める人材像」を整理し、ゴール・目的から逆算して計画を作成するのがポイントです。なお、新人教育をできるだけ効率化して実施したいと考えている方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:新人教育を効率化する方法は?カギは動画マニュアル!
計画に沿ったマニュアルを整備する
策定した教育計画からどのようなマニュアルが必要なのかを洗い出し、必要なマニュアルの作成・整備を進めていきましょう。マニュアルが不足していると教育担当者への質問が発生したり、誤った作業をしてしまったりするなど、余計な手間が発生してしまいます。
最低限用意しておきたいマニュアルの種類としては以下の通りです。
- 業務マニュアル:業務全体のおおまかな進め方や流れ、基準など
- 取扱説明マニュアル:業務で用いるツールやシステム、設備機器などの操作方法など
- 教材・訓練用マニュアル:社会人としての精神やビジネスマナー、業務の基礎知識など
なお、「わかりやすいマニュアルを活用する」でも紹介したように、紙ではなく動画を活用したマニュアルの作成が増加しています。動画マニュアルについて詳しく知りたい方は、活用するメリットや導入のステップをまとめた以下の資料をご覧ください。
新人の成果を評価・FBを行い、改善のPDCAを回す
新人社員の業務内容や成果物に対しては、必ず目を通して評価・フィードバックを実施しましょう。仕事や作業の要領を掴めておらず、自身の成果物の良し悪しを理解できていないため、基準を把握するうえでも非常に重要な工程です。
評価・フィードバックをする際には、改善点の指摘のみにならないよう工夫し、悪かった点とあわせて良かった点を伝えることで、自信やモチベーションの向上につながります。
また、同じようなミスを繰り返さず、常に良い成果物や作業ができるようにするためにも改善に向けたPDCAを回すことも重要です。PDCAの意味やなぜPDCAが改善する上で重要なのかを説明しておきましょう。
教育計画・教育マニュアルの改善を行う
当初立てた教育計画や作成した教育マニュアルは、定期的に見直しを進めて改善を繰り返していきましょう。社内事情や方針の転換、業務内容の変更などの様々な理由によって、計画やマニュアルの内容は古くなります。改善・改訂を行わずにそのまま活用していると、形骸化してしまい意味のない計画・マニュアルになってしまうことも。
変更点や方針の転換などがあった場合にはもちろんですが、半期に1度などのタイミングで定期的な見直しをおすすめします。なお、改善や改訂を行った場合には従業員への周知も忘れずに行いましょう。
新人教育の失敗例
新人教育が失敗する場合には主に人が原因の場合と仕組みが原因の場合に分けられます。ここではそれぞれの失敗例について解説します。
新人教育の失敗例や失敗が引き起こす課題について、以下の記事でも詳しく解説しています。併せてご参考ください。
関連記事:新人教育の進め方で気をつけるべきポイントとは?ダメな例や失敗しないマニュアル活用法を解説!
人が原因の失敗例
新人教育における人的な失敗例として、教育担当者の指導方法に問題があるケースが挙げられます。新人目線ではなくベテランの目線やスピードで教育を進めてしまうことは、新人がついていけない大きな原因です。
近しい事例として、トーヨーケム株式会社ではOJT中心の新人教育を実施してましたが、人や物の動きが多い現場作業を伝える際に担当者によってバラつきがあり、新人の業務習熟度に差が発生する課題を抱えていました。技術伝承が進まず、業務の属人化や不安全行動にもつながるリスクがあると感じていたそうです。
そこで、ノウハウ伝授、技術伝承を推進するべく、新人教育に「tebiki現場教育」を導入。OJTの時間が削減され、属人化の解消や技術伝承にもつながり始めていると実感しています。同社の事例は以下のリンクをクリックするとご覧いただけます。
インタビュー記事:新人からベテランまで700名を超える組織教育のグローバルスタンダードを目指す
仕組みが原因の失敗例
新人教育における失敗の多くは個人の責任だけでなく、仕組みの問題に起因することがあります。オフィスでの忙しさや教育体系の不備が新人教育の質を低下させる主な要因となることも。
典型的な例として現場が常に忙しく、教育担当者に適切な時間やリソースが割り当てられないことが考えられます。日々の業務に追われる中で新人教育に十分な時間を確保することが難しい場合があるでしょう。結果として、教育担当者は中途半端な教育を行うことになり、新人は必要な知識やスキルを十分に身につけられません。
実際に、日本クロージャー株式会社では工場が複数拠点にあることで、新人教育に関する情報の共有がスムーズにできていない課題がありました。また、新人社員からの質問に対して、担当者が忙しくすぐに回答できずに待たせてしまうことも。
そこで、クラウド上で動画マニュアルを管理できる「tebiki現場教育」を導入。閲覧したいマニュアルをすぐに検索でき、動画を見せるだけで作業内容を理解してもらうことに成功しています。同社の事例は以下のリンクをクリックするとご覧いただけます。
インタビュー記事:新人OJTの7割を動画に置き換え。教育の手間を大幅に削減しました。
業界別にみる新人教育を行うコツ
新人教育のコツは業界によって異なる場合があります。ここでは以下3つの業界における新人教育のコツを解説します。
製造業
製造業における新人教育では、出身学校や背景に関わらず、それぞれの新人に合わせた教育が重要です。新人の中には工業高校や工学部など、技術的な基礎教育を受けてきた者もいれば、全く異なる分野から転職してきた者もおり、それぞれの知識レベルやスキルは大きく異なるからです。
製造業で現場教育が上手くいかない原因の詳細や具体的な改善策は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
たとえば、基本的な工具の使用方法や安全知識に精通している新人には、より高度な技術や特定の機械操作技術に焦点を当てた教育を行います。結果として、すでにある程度の知識を持つ新人は自分のスキルをさらに伸ばすことが可能です。
一方で技術的な背景がない新人に対しては、基本的な工具の名前や使用方法から教える必要があります。個人保護具の正しい着用方法や、工場内での安全ルールといった安全に作業を行うための基礎知識についても詳しく説明する必要もあるでしょう。新人に合わせた教育を実施することで学習効果を最大化し、いち早く新人を即戦力とすることが期待できます。
製造業の新人教育を成功させるには、新人教育がうまくいかない製造現場にありがちな「根本的な要因」を解消することが急務です。その根本的な要因と具体的な改善策を凝縮した資料「新人教育に失敗する製造現場に潜む3つの構造的要因と新しい教育アプローチ」もあわせてご覧いただくと、新人教育の解決の糸口が見えるはずです。
製造現場における新人教育問題を改善したい方は、以下の画像をクリックしてダウンロードしてみてください。
介護業
介護業界における新人教育では、体格や性別に応じた介護方法の指導が重要です。介護職は肉体的な力が必要とされる職種であり、特に高齢者の移動や支援にはある程度の体力が求められるからです。
男性職員の場合、元々の体力や力の強さを活かして比較的容易に高齢者を支え、移動させることが可能です。しかし女性職員や体格の小さい職員の場合は、力の使い方や介護の技術に工夫が必要となります。たとえば、小柄な女性の新人職員に対しては体を支える際の最適なポジション取りなど、女性や体格が小さい人に適した方法を重点的に教えることが重要です。
高齢者向け、障がい児・者向けの事業を展開している「社会福祉法人 若竹大寿会」では、拠点ごとにマニュアルが異なっていたり、新人教育に必要以上の時間がかかっていましたが、動画マニュアルの活用によって介護技術を統一し、教育課題の改善につなげています。同社の事例を詳しく知りたい方は、「介護技術を動画マニュアルで統一。法人全体で文化を作り上げる!」の記事もご覧ください。
飲食業
飲食業界における新人研修では、お客様へのおもてなしのための動作の習得が重要です。飲食業では、お客様に満足いただくための接客サービスが売り上げと顧客満足度に影響を与えるからです。
たとえば、フォーマルなレストランでは丁寧な敬語やお客様への配慮深い接客が求められる一方で、カジュアルなカフェでは、フレンドリーで親しみやすい接客が好まれます。そのため、新人には店舗独自のサービススタイルを教育することが重要です。
横浜市を中心に飲食店を展開する株式会社ハングリータイガーでは、接客における細かい所作、調理手順など人の動きなどの細かい部分が新人にうまく伝わらない課題を抱えていたものの、動画マニュアルの活用によって細かな業務手順を新人に教育することに成功しています。
同社の事例を詳しく知りたい方は、「マニュアル作成やOJTの工数削減!接客の所作や業務の動きを伝えるには動画がベスト」の記事もご覧ください。
【まとめ】新人教育の課題はtebiki現場教育で解決しよう
新人教育は企業の成長力・競争力を維持する上で不可欠な要素です。目標や計画を立てていない状態で新人教育を進めても思うような育成は望めないため、この記事で紹介してきたようなコツや進め方を踏まえた上で計画的に進めるのが大切です。
なお、新人教育への人的なリソースを抑えて効率的に進めるためにも、動画マニュアルの活用は非常に有効な手段と言えるでしょう。実際に企業のOJTでも導入されており、改善された実績があることからもその有効性がわかります。
本記事で紹介した「tebiki現場教育」は、新人教育の課題解決に導く最適なツールです。導入を検討している方は、tebiki現場教育で解決できる課題や得られる効果をまとめたサービス資料をご覧ください。以下の画像をクリックするとダウンロードできます。