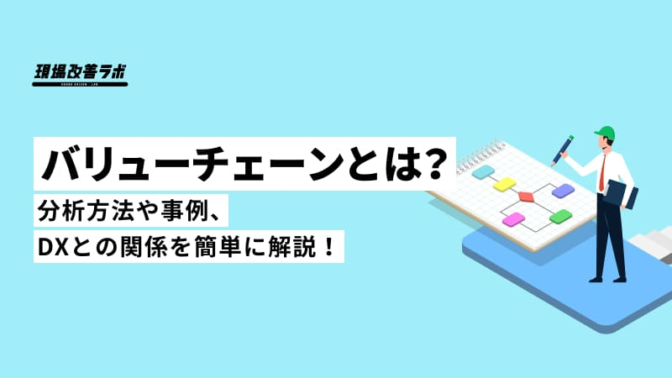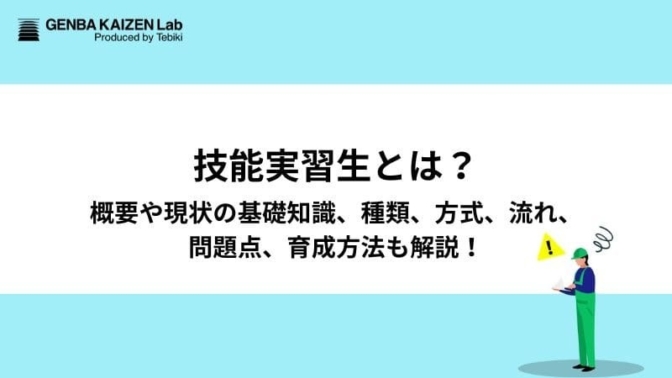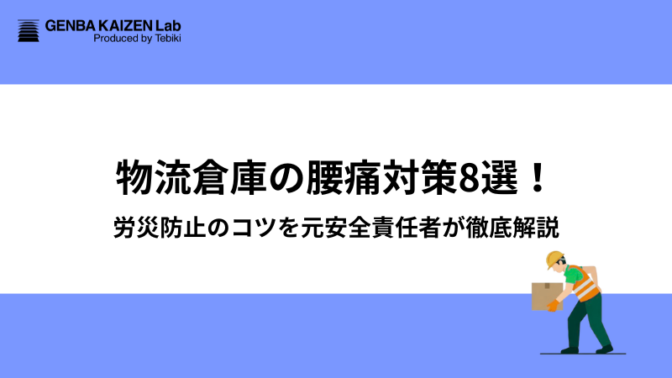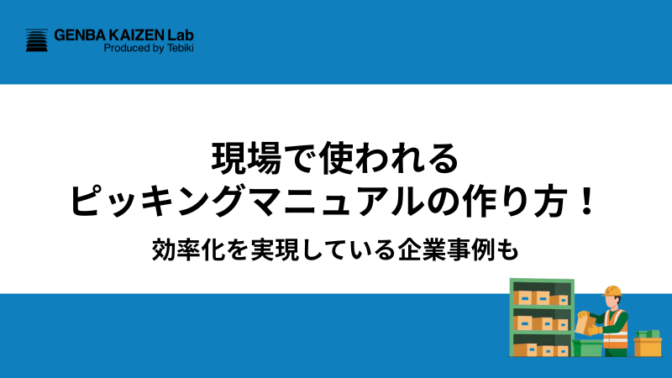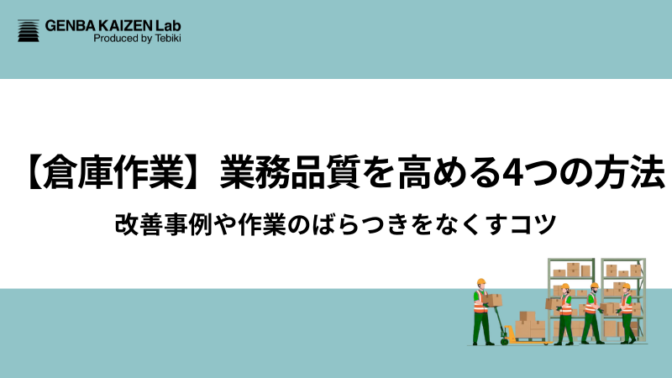かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
業務品質を向上させることにより、より良い製品・サービスの価値を提供することができ、顧客満足度の向上・生産性の向上・コスト削減などにも繋がります。企業の継続的な成長や競争力の維持などにも寄与する非常に重要な要素です。
この記事では、業務品質を向上させる重要性や向上させる上で重要な視点、業界ごとの具体的な対策などについて解説していきます。あわせて、業務品質の向上につながるツールも紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
業務品質を向上させることは、企業の競争力に不可欠です。 しかし、その大前提である「ルール」が無視されていては、品質向上は実現できません。
この「ルール無視」の根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
目次
業務品質とは?
業務品質とは、企業や組織が提供するサービスや製品の品質だけでなく、製造や提供に関わる業務そのものの品質を指します。業務品質の向上には「業務」と「製品・サービス」の2つの側面に分けられます。
業務品質を向上させる上では、作業手順書やマニュアルなどが非常に重要です。紙のイメージが強いかもしれませんが、電子マニュアルも普及しており、マニュアルを動画化するケースも多くあります。動画マニュアルでは、紙では伝わりにくい細かい動きや微妙なニュアンスを動画で伝えられて従業員の理解度も高まり、結果として業務品質の向上が見込めます。
実際に動画マニュアルを導入している「新日本工機株式会社」では、動画に置き換えたことで標準化された作業を正確かつ簡単に伝えることができ、作業品質も安定するようになったと効果を実感しています。
業務品質の向上に向けて、動画マニュアルも選択肢の1つにしたい方は、紙マニュアルとの比較やメリット、導入ステップなどをまとめている以下のガイドブックをクリックしてご覧ください。
業務そのものの品質向上
業務の品質向上は、日常的な業務の手順やプロセスを指し、クオリティの向上に努めることです。例えば、複雑な作業手順を見直す、作業工程の中で不要な作業を排除する、担当者によって作業時間や成果にバラつきがあるなどが挙げられます。
これらの業務品質を向上させるうえで参考になるのが、トヨタ生産方式が源流とされる3M(ムリ・ムダ・ムラ)の排除です。徹底的なムダの排除を追求することで、高品質・低コスト・短納期の実現が見込めます。3Mについてより詳しく知りたい方は、製造業の経営コンサルティングに従事している専門家の動画セミナー「3M(ムリムダムラ)の視点と改善 製造業の品質向上と生産性向上への鍵」も合わせてご覧ください。
製品・サービスの品質向上
製品・サービスの品質は顧客からの評価や売上によって向上の度合いを測定することが可能です。
製品であれば、ユーザーにとって魅力的な製品を設計・製造することが品質向上の目標となります。製品の品質が高ければ顧客満足度やリピート購入率の向上が見込めるでしょう。
サービスの場合は、顧客のニーズに応じたサービス提供やアフターサービスを徹底することで品質の向上が期待できます。製造業の例として、自動車産業で新しい技術導入や製品の耐久性、安全性を向上させることで製品やサービスの品質を上げることができます。
設計された「耐久性」や「安全性」も、現場が「ルール」を無視すれば実現しません。この「ルール無視」の根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
業務品質の向上に必要な視点7選
業務品質向上に必要な視点として、以下の7つが挙げられます。
可視化
製造業における品質向上には、プロセスやデータを明確に可視化することが不可欠です。可視化とは情報やデータを視覚的に表現し、全体の流れや状況を一目で把握できるようにする手法を指します。
例えば、製造ラインの動きや生産設備の稼働状況、リソースの配分などをグラフやダッシュボードで表示することにより、課題やボトルネックを迅速に特定することが可能です。可視化を行うことで組織全体の意識が高まり、迅速な意思決定や効果的な改善策の実施ができます。
製造業での可視化を実現したい方は、メリットや導入・運用時の注意点などを詳しくまとめた以下の関連記事もあわせてご覧ください。
関連記事:製造業の「見える化」実現方法は?工場事例や現場DXツールも解説
定量化
定量化とは、品質向上のための具体的な指標や目標を設定することであり、製造プロセスや業務の状況を具体的な数値で捉え、分析や評価の基盤とするために必要な指標です。
例えば生産量や不良品率、稼働率などを設定し、数値を定期的にモニタリングすることで進捗状況や課題を明確に把握できます。定量化により、目標達成のための具体的なアクションや改善策を計画的に進めることが可能です。
課題化
課題化とは、製造プロセスや業務の中で発生している問題・課題を明確に特定し、解決するための取り組みを計画することです。
課題化には現状の分析やボトルネックの特定、改善策の立案が含まれ、同じ目標に向かって取り組むことができ、品質向上の取り組みが効果的に進められます。
関連記事:【品質改善】製造業の品質向上策9選!改善事例も解説
実践化
実践化とは、策定した計画や改善策を実際の現場で実施することです。実践化にはPDCAサイクルを基盤とした継続的な改善活動が必要です。
実践化を行うことで計画やアイデアが現場の実情に合致しているかを確認し、必要に応じて計画の修正や再策定を行います。
標準化
標準化とは製造プロセスや業務手順を統一する取り組みのことで、標準化により業務の効率化や品質の安定化を図ることが可能です。標準化された手順やマニュアルをもとに業務を行うことで、ミスの削減や業務のスムーズな進行が期待できます。
品質のバラつきは企業にとって見過ごせないポイントなので、バラつきを抑えて「標準化」することが重要です。以下の解説動画では、元トヨタ自動車九州株式会社で品質保証部や品質管理部、組立部に従事した古里氏による「トヨタ式標準化の進め方」をご覧頂けます。
興味がある方は、以下のテキストをクリックして解説動画を視聴してみてください。
>>「品質のバラつきを抑える「トヨタ式標準化」の進め方」(視聴無調)を見てみる
自動化
自動化は人の手を介さず業務を効率的に行うための取り組みです。例えば、AIを活用して定型的な業務を自動化することにより業務の効率化や品質の向上を実現することが可能です。自動化への取り組みにより、既存業務を改善して人員の削減にも寄与する省人化も見込めます。
省人化が実現することによって、業務品質の担保はもちろん、人手不足の解消や生産性の向上などの副次的な効果を得ることにもつながります。省人化については、進め方のポイントなどを詳しく解説した専門家による動画を用意しているので、気になる方は以下をクリックして動画を視聴してみてください。
定着化
定着化とは、一度取り組んだ改善策や新しい方法を組織の文化や日常業務として根付かせることです。製造業において、新しい技術や手法を導入するだけでは持続的な品質向上は難しく、定期的な教育やトレーニング、組織全体でのコミュニケーションが不可欠です。
以下の資料も併せてご覧ください。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
業界別に見る業務品質向上の具体例と方法
業界別に見る品質向上の具体例と方法を解説します。解説する業界は以下4つの業界です。
- 製造業
- 物流業
- 宿泊業
製造業
製造現場では、細々とした作業が多く複雑な手順を要することが多く、人によって理解度や習熟度に差があり、業務品質が安定しない場合もあるでしょう。
新日本工機株式会社では、作業手順が標準化されない課題に対し「標準化プロジェクト」を立ち上げ、業務品質の向上に取り組んでいます。プロジェクトの中では、紙のマニュアル・手順書ではなく動画マニュアルを活用しているのも特徴です。
▼インタビュー動画:新日本工機株式会社▼
プロジェクト内で動画を活用することによって、現場のノウハウを可視化でき、中堅や若手に対する技術伝承も以前と比べてスムーズに進められて作業品質の安定につながっています。同社の事例を詳しく見てみたい方は、「新日本工機株式会社のインタビュー記事」からご覧ください。
物流業
物流における品質=荷役作業や輸送、物流サービスの品質であり、品質が低い場合には納期の遅れや取扱い品の破損、配送先のミスなど、重大なトラブルに発展する可能性が考えられます。ピッキングミスなども業務品質の低下につながるでしょう。
物流品質向上の取り組みとしては、倉庫内のレイアウトを見直して作業動線を確保する、作業マニュアルを整備するなどの対策が効果的です。
実際に、株式会社ロジパルエクスプレスでは、拠点ごとにマニュアルやルールが統一されておらず、作業手順や業務品質にバラつきが発生していた課題に対し、マニュアルの動画化で業務品質の向上を実現しています。
安全意識の向上や業務ノウハウの可視化にもつながったと語る同社の事例を詳しく見てみたい方は「株式会社ロジパルエクスプレスのインタビュー記事」からご覧ください。
宿泊業
顧客満足度の向上やリピート利用の促進に直結するため、宿泊業でも業務の品質向上は非常に重要です。宿泊施設を利用する際、顧客は快適で安全な滞在を期待しています。
具体的な取り組みとしては部屋の清掃品質の向上やアメニティの質的向上が考えられます。また、スタッフの教育やトレーニングもサービス品質向上のために重要です。
全国100を超える施設運営を手掛ける東急リゾーツ&ステイ株式会社では、個人ごとにサービス品質のバラつきが課題でした。サービス品質の均質化に向けた一環として、マニュアルを作成しやすく、汎用性が高い動画マニュアルを導入。
マニュアルを統一管理することで、業務の平準化・標準化を実現し、品質向上を実現しています。個々のスキルに応じた教育プログラムを構築したいと語る同社の事例を詳しく見てみたい方は、「東急リゾーツ&ステイ株式会社のインタビュー記事」からご覧ください。
ここまで紹介した業界ごとの業務品質の向上対策では、いずれも動画マニュアルが活用されているのが共通しているポイントです。実際にどのような動画マニュアルが活用されているのか見てみたい方は、実際の業務で使われているサンプル集がオススメです。
以下の画像をクリックすると、サンプル動画集をご覧いただけますのでぜひご活用ください。
業務品質の向上にはツールの活用がおすすめ
業務品質は何かしらの施策を講じて、対策をしなければ向上させることは困難であり、対策したとしてもすぐに効果が現れるわけではありません。
少しでも効率化するために有効な手段として、専用のITツールの導入がおすすめです。ここでは、標準化/定着化に欠かせない動画マニュアルについて紹介していきます。
標準化/定着化に欠かせないツール:動画マニュアル
業務の標準化や定着化に欠かせないツールは、マニュアルを動画で作成できる動画マニュアルです。紙マニュアルの場合、読み手によって理解度にばらつきが生まれてしまい標準化できない、作業変更があった際に新たな作業が定着しないなどが考えられます。
しかし、紙のマニュアルを動画化することによって、以下のようなメリットを得られます。
- 文章では表現しにくい詳細な動きを動画で伝えられる
- 就業前後や休憩時などのスキマ時間で繰り返し学べる
- 作業手順変更の際、共有フォルダに格納するだけで更新・共有ができる
結果として、業務品質の向上にもつながるでしょう。次の見出しでは、動画マニュアルを活用して、実際に業務品質を向上させた事例について紹介していきます。
動画マニュアルで業務品質を向上させた事例
動画マニュアルを活用している企業事例として、サラヤ株式会社の事例を紹介します。同社では、紙のマニュアルでは指示が伝わりにくい点や、マニュアル化されていない業務を口頭のみで伝えていたために品質にばらつきが発生するなどの課題を抱えていました。
そこで、従業員により詳しく作業内容を伝えることを目的に動画マニュアルを導入。紙では表現しにくい動きや見せ方などを動画であればそのまま伝えることができ、作業担当者の認識を揃えられ、業務品質の向上につながっています。同社の事例を詳しく読みたい方は、「サラヤ株式会社のインタビュー記事」をご覧ください。
業務品質の向上を実現する「tebiki現場教育」
「【業界別】業務品質を向上させる具体的な対策」や「業務品質の向上にはツールの活用がおすすめ」でも紹介したように、業務品質を向上させるうえでは、多くの企業で導入されていることからも分かるように、動画マニュアルによるアプローチが最適です。
動画と聞くと「編集が難しいのでは…?」と感じる方もいるかもしれませんが、tebiki現場教育では誰でもかんたんに動画マニュアルの作成/活用ができます。
▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼
tebiki現場教育では、以下のように幅広い機能を搭載しており、業務品質向上につなげることができます。
- 映像編集未経験者でも「かんたん」に使える編集画面
- 音声読み取りによる字幕の自動生成機能
- 字幕を100ヶ国以上の言語へ瞬時に自動翻訳
- 一部言語は字幕の読み上げ機能に対応
- テスト機能やレポート機能による理解度・学習進捗の可視化
- スキルマップなどスキル管理機能による教育計画と実行
- 半永久的に続く専属サポート
機能ごとの詳しい特徴や活用事例などを知りたい方は、詳しく紹介しているサービス資料をご覧ください。以下の画像をクリックしてダウンロードいただけます。
業務品質の向上に向けたステップ
業務品質向上するために行うべき3つのステップは以下の通りです。
業務品質を改善する部門を設置し担当責任者を決める
製造業における業務品質の向上は一部門だけの取り組みだと限界があるため、組織全体の取り組みとして進める必要があります。
具体的には主体となる推進部門を設置し、部門の責任者を明確にすることが重要です。推進部門と責任者が業務品質向上の主導権を握り、全社的な取り組みを引っ張ります。
例えば、製造業では生産ラインの効率化や欠陥品の削減など具体的な品質向上の目標を設定し、目標を達成するための戦略を策定する役割を担います。
計画を作成し改善マニュアルを作成する
品質向上の取り組みを進めるためには、具体的な計画とその実行手順を示すマニュアルの作成が不可欠です。
製造業の例で考えると、生産ラインの効率化を目指す場合、どの工程をどのように改善するのか、どのような機械や技術を導入するのかなど具体的な計画を立てる必要があります。加えて、計画にもとづき実際の作業手順や注意点をまとめたマニュアルを作成し、従業員に周知することで品質向上の取り組みをスムーズに進めることが可能です。
品質向上にはマニュアルによる標準化が不可欠です。しかし、どれほど精緻なマニュアルを作っても、現場で運用される中で手順が「形骸化」してしまえば意味がありません。
周知したはずの手順がなぜ守られなくなるのか。現場で静かに進行する形骸化の実態と、それを防ぐ対策を以下の資料で解説します。
>>繰り返される品質不良~作業手順は静かに形骸化していた~を見てみる
従業員へ発信・周知する
従業員一人ひとりの行動が品質向上に直結するため、品質向上の取り組みを成功させるためには従業員全員が取り組みの意義や目的を理解し、協力して行動することが必要です。
製造業でも生産ラインの作業者や品質管理部門のスタッフなど多くの従業員が業務に関わるため、全員が同じ方向を向いて取り組むことが重要です。そのため、計画やマニュアルを作成した後は従業員に発信し、周知することが必要です。
具体的には研修やミーティングを通じて、品質向上の取り組みの内容や意義を伝え従業員の理解と協力を得ることが求められます。
品質が改善されているか定期的にモニタリングする
従業員への発信・周知をして終わりにするのではなく、実際に品質が改善されているのかという点までモニタリングをしましょう。結果がどうなっているかを把握することで、さらなる業務品質や効率の向上につなげられます。また、継続的な改善活動として取り組むことも可能です。
業務品質向上に向けたPDCAサイクルを回し続けられるような体制を構築していきましょう。
tebikiを使って業務品質向上を実現しよう[まとめ]
業務品質とは企業が提供するサービスや製品の品質だけでなく、製造や提供に関わる業務そのものの品質を指します。業界別に見ると製造業はもちろん、介護や飲食産業、宿泊業などの業界で品質向上の取り組みが行われています。
業務品質を向上させるためには業務の「可視化」や「定量化」、「標準化」、「自動化」などの7つの視点が必要です。また、業務品質を向上させるためのステップとして「業務品質改善する部門を設置し、担当責任者を決める」ことを進め、次に「計画を作成し、改善マニュアルを作成する」ことが求められます。さらに、そのマニュアルや取り組みを「従業員へ発信・周知する」ことが挙げられます。
業務品質向上のためのマニュアル作成には、動画マニュアルtebikiがおすすめ。tebikiは動画マニュアルを簡単に作成でき、業務の手順やポイントを視覚的に伝えられます。
tebikiの機能詳細や費用対効果については、以下の資料で詳しく解説しています。「動画マニュアルの導入効果を具体的に知りたい」「自社の課題に適した活用事例を確認したい」とお考えの方は、是非ご参考ください。
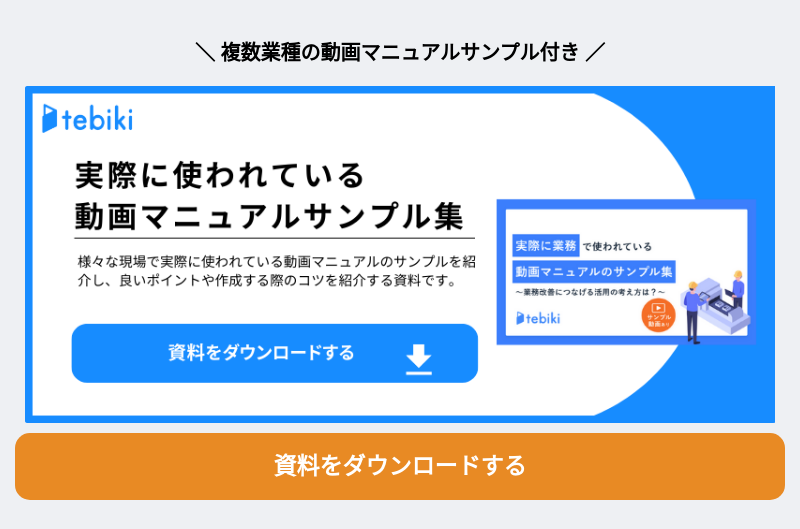


-1.png)